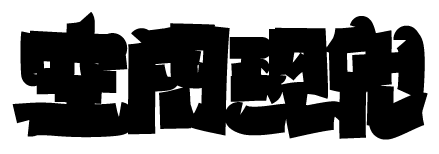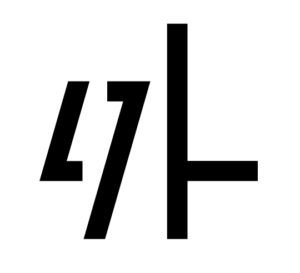Palm
1.Singou
2.Mure
3.Menomae
4.Hi-Vision
5.Sougei
6.Chigaukoto Wo Kangaeyo
2019.5.19
Digital / Vinyl LP
Label : Ideologic Organ
Recorded at Soto, Kyoto JP
Recorded and Mixed by Bunsho Nishikawa
Mastered and Cut by Rashad Becker at Dubplates & Mastering Berlin
Photographs by Mayumi Hosokura
Graphic Design by Shun Ishizuka LP
コード・デコード・エンコード
このアルバムから聴こえてくる音楽は,過去の空間現代とは大きく異なっている。『PALM』に収録された六つの楽曲は、最初期のようなジャパニーズ・オルタナティヴ・ロックの突然変異の範疇からも、セカンドアルバムで切り拓いた、電子音響におけるグリッチやダブステップ、フットワーク等のリズム構造を3ピース・バンドに強引に落とし込む野心的な試みからも、その延長線上で発明された、レパートリーをパーツに細分化して、その都度のライヴの演奏時間に再編成=メガミックスする途方もないアイデアからも、或いはMoe and ghostsとのコラボレーションアルバムに結実した、ラップ、ヒップホップとの有機的融合からも、すでに遠く離れている。いや、精確に言えば、それら過去のあれこれをしかと踏まえつつも、まったく新たな次元へと一気に跳躍してみせたのが、この作品『PALM』なのである。
そもそもこれは「音楽」なのだろうか。この問い方が無意味なら、こう言い換えよう。これらは果たして「曲」なのだろうか。私はこのアルバムを最初に聴き通したとき、まるでモールス信号みたいだ、と思った。ズレを伴った反復、というスタイルは彼らが以前から持っていたものだが、ここでは遂にズレ=差異化の運動が反復性を完全に凌駕してしまい、もはやミニマリズムの定義では説明出来ない段階に至っている。それでいて全体としては、どのトラッックも極めて淡々としており、表面的には非常にモノトナスな印象を与える。しかし、それは感覚が与える誤解に過ぎない。比喩的に言えば、ある程度離れた距離から眺めていると、川の流れは一定でさしたる変化がないように見えるが、近づいていくとそこには無数の渦やうねりや波立ちが犇めき衝突し合っており、微細なレベルで激しい変化と運動が存在していることがわかってくる、というような。『PALM』はクローズアップ的な,顕微鏡的な聴取を要求する。どの部分を抽出してみても、そこには思いがけないダイナミズムが隠されている。
モールス信号の比喩に戻ろう。特筆すべきことは、ここではギター、ベース.ドラムスのいずれもが個々に信号を発しているということである。しかも、それらは必ずしも同じメッセージを発信しているわけではない。もちろん合致するところもあるのだが、あたかも各自がバラバラに別々のモールス信号を奏でているかのようなのだ。更に言えば、それらの信号は、しかるべき対照表をあてがえば解読出来るのでさえない。各楽器が発信するモールス信号は、それ自体が暗号化されているのだ。そして暗号をデコードするためのプログラムも、おそらくひとつではない。
暗号化されたモールス信号としての音楽。これが比喩であるのは、当然のことながら、空間現代はサウンドを言語のように使用しているのではないからだ。仮にデコードが可能だったとしても、読み解かれたメッセージの内容それ自体に意味があるわけでも、最終的にそれが十全に伝達されることが求められているのでもない。各曲にはタイトルが付けられているし、歌詞らしきものやヴォーカルパートだって存在しているのだから、そこにはそれぞれ何かしらの言語的要素が潜在していることは確かだろうが、しかし敢えて言ってしまうなら、実のところそこにはコミュニケーションを要請する主題など何もありはしない。それらは差異と反復が導出した運動の軌跡、イメージの残像でしかない。だが、それでも単なる記号性とは違う動機が残存していることも確かである。従って、私が『PALM』はモールス信号のように聴こえると述べたとき、そしてそれらが暗号なのだと比喩的に推定したとき、デコードへの欲望が封じられてはいない。むしろ積極的にこれらの音たちはリスナーに働きかけてくる。さあ,読めるものなら私たちを読んでみてください、聴取という受動的行為が暗号解読という能動的行為と同義となる稀有なる体験にようこそ、と。
然るに、空間現代のこの新しい作品は、従来の音楽とはかなり違った意味で、集中的な聴取と、再帰的な聴取を強く喚起する。『PALM』を再生するということは、六つのトラックを私たちが読むことであると同時に、それらが私たちを読むことでもあるのだ。音楽にスキャンされるという又とない感覚。音楽をデコードすることと、音楽によってエンコードされること。念のために言い添えておけば、それらはもちろんフィジカルな経験でもある。何しろ、これらの楽曲はおそらくライヴでも演奏されるのだ。少なくとも幾つかのトラックは、ダンサブルでさえある。そこで惹起されるダンスは、私たちが踊ってきたものとはほとんど似てはいないけれども(たとえばフットワークが複雑系をシンプリシティに閉じ込めたのだとしたら、空間現代はそのリバースモードを提示しているのだと言ってもいい)。
このアルバムで、空間現代は進化の階梯を何段も飛ばして、これまで誰も足を踏み入れたことのないステージに立った。この前人未到は、けっして派手なものではない。だがしかし、これは真に驚嘆に値する冒険である。もっと素朴に、こう言ってしまってもいい。こんな「音楽」は、こんな「曲」は、いまだかつて聴いたことがない。
佐々木 敦
Kukangendai is a kick ass rock trio from Kyoto (Tokyo transplants). When I first hear this band live I was instantly transfixed by their minimalist yet illusory primitive, polyrythmic and structural, memory evoking rock narratives. Their energy is completely and transparently palpable yet handled with restraint of the pleasure of a disciplined form dealing with time and articulation. They are a power trio of bass, drums and guitar but the music they play is as much the limbic system of a forest than it is a geode.
They started in 2006. They left Tokyo to Kyoto and started the cult venue Soto (“Outside”) “to listen to music they hadn’t heard yet” a few years later.
They collaborated with Ryuichi Sakamoto last year. They reminded me of James Brown on a heavy binge of Bastro, there’s a deep current of both archaic musical tastes and the human desire for articulating that archaism in there, but you shake your ass and get the shouting in… in a punk basement …
13th century version of Breadwinner, the bare soul version. I’m honoured and proud to work with this tribe, and to count them amongst friends.
Stephen O’Malley